
「作り置きしたいけど、何をどう保存すればいいか分からない…」そんな悩みを持つ方は多いのではないでしょうか?忙しい毎日でも手軽に美味しく、しかも長持ちする保存食があると嬉しいですよね。
本記事では、初心者でも簡単にできる醤油を使った保存食レシピを15品ご紹介。常備菜・漬物・佃煮・醤油麹といった幅広いジャンルのレシピから、保存方法のコツまで丁寧に解説しています。
「ごはんが進む常備菜を作りたい」「時間のあるときに作り置きしたい」そんな方にぴったりの一冊。まずは気軽に読み進めて、保存食のある暮らしをはじめてみませんか?
醤油の保存食が人気の理由とは?
日々の食卓に欠かせない調味料「醤油」。この身近な存在が、実は保存食としても非常に優秀であることをご存じでしょうか?
最近では、健康志向や時短志向の高まりから「醤油を活用した保存食」の人気が高まっています。ここでは、その理由を詳しく見ていきましょう。
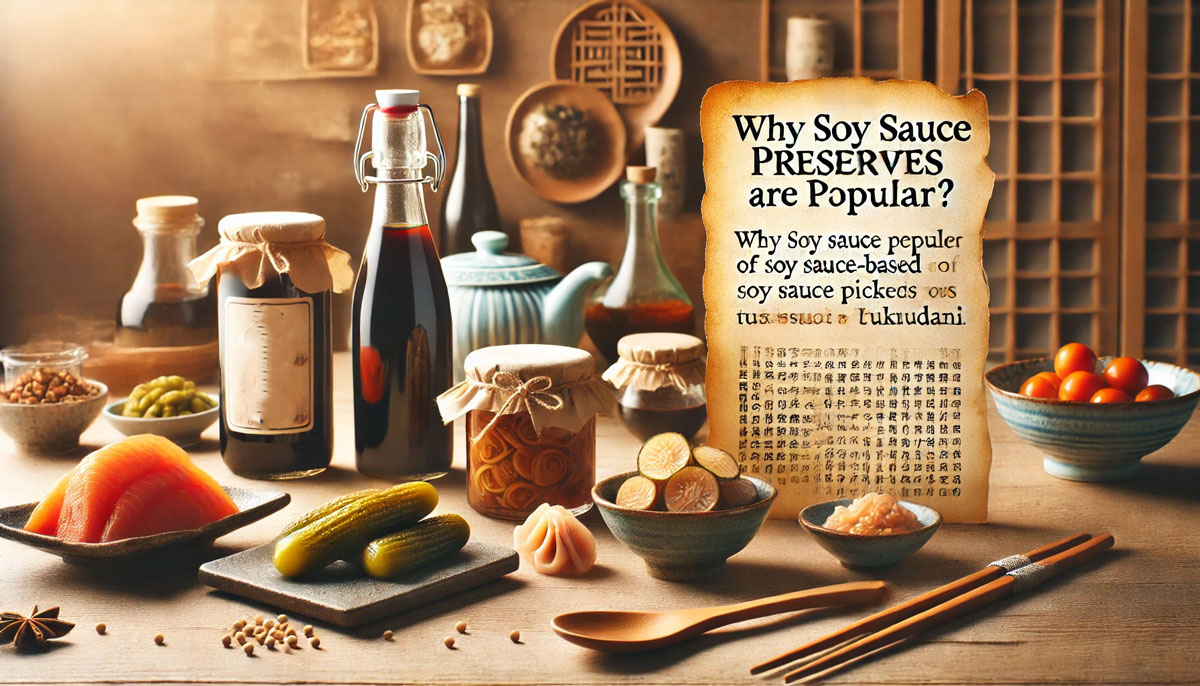
和食の基本「醤油」は長期保存に最適
醤油は、日本の食文化に根ざした調味料であり、昔から保存性の高い食品として親しまれてきました。
その秘密は、醤油自体が発酵食品であり、塩分と微生物の働きによって腐敗しにくい性質を持っている点にあります。
保存食として醤油を使うと、素材の味に深みが出るだけでなく、雑菌の繁殖も防げるため、長期間保存できるというメリットがあります。
特に、野菜や魚介類、卵などを醤油に漬ける「醤油漬け」は、冷蔵保存で1週間〜10日ほど日持ちするレシピも多く、安心してストックできます。
また、冷凍保存と組み合わせることで、数週間〜1ヶ月以上保存できるものもあるため、食材ロスの削減にもつながります。
以下は、醤油保存食の保存期間の目安を一覧にした表です:
| 保存食の種類 | 保存方法 | 保存期間の目安 |
|---|---|---|
| 醤油漬け(野菜) | 冷蔵 | 約5〜10日 |
| 醤油漬け(卵黄) | 冷蔵 | 約5日 |
| 醤油麹 | 冷蔵 | 約2週間〜1ヶ月 |
| 佃煮(醤油ベース) | 冷蔵 | 約10日〜2週間 |
| 冷凍した醤油漬け | 冷凍 | 約1ヶ月 |
このように、保存方法によって日持ち期間を調整できるのも、醤油の魅力の一つです。
毎日のごはん作りがラクになる作り置き術
忙しい現代人にとって、毎日の献立を考えるのは大きな負担。そんな中、「作り置き」は大きな味方です。特に、醤油を使った保存食は下味がしっかり付いているため、加熱するだけ・盛り付けるだけで一品が完成します。
たとえば、前日に作っておいた「なすの醤油煮」は、翌朝のお弁当にも最適。再加熱すれば、夕食の副菜としてもそのまま使えます。
さらに「醤油麹」は、肉や魚に漬けて焼くだけで、旨味たっぷりのメインディッシュに早変わり。手間がかからず、家族にも喜ばれるのが嬉しいポイントです。
忙しい日のごはん作りが時短になり、しかも栄養もキープできるという点で、醤油の保存食は非常に実用的です。
また、醤油の深い味わいは飽きにくく、食欲をそそるため、家族全員が満足できる献立に仕上がります。作り置きしておけば、調理の手間だけでなく、買い物の回数も減らせて経済的ですね。
このように、「醤油の保存食」は、和食文化の知恵と現代のライフスタイルにマッチした、まさに“最強の作り置き”レシピ。
次回は、実際に簡単に作れる「醤油漬け」「佃煮」「醤油麹」のレシピをご紹介します!
定番!醤油を使った常備菜レシピ
毎日の食卓やお弁当に欠かせない常備菜。その中でも、醤油を使った常備菜は「日持ちがする」「ごはんが進む」「簡単に作れる」といった理由で、多くの家庭に支持されています。ここでは、冷蔵庫に常備しておくと重宝する、定番の醤油レシピを3つご紹介します。

なすの醤油煮
とろりと柔らかく仕上がる「なすの醤油煮」は、冷やしても美味しく、夏場にもぴったりな一品です。
【材料(2〜3人分)】
・なす 3本
・だし汁 200ml
・醤油 大さじ2
・みりん 大さじ1
・砂糖 小さじ1
・ごま油 適量
【作り方】
-
なすは縦半分に切り、皮に浅く切り込みを入れて食べやすい大きさに切る。
-
フライパンにごま油を熱し、なすを焼き色がつくまで焼く。
-
鍋にだし汁、醤油、みりん、砂糖を入れて加熱し、なすを加えて弱火で10分ほど煮る。
-
粗熱が取れたら冷蔵庫で保存。翌日以降がより味がなじんでおすすめ。
作り置きしておくと、副菜・お弁当・冷やしうどんのトッピングなど、様々に活用できます。
れんこんのきんぴら風醤油炒め
シャキシャキ食感が魅力のれんこんは、きんぴら風に炒めることで、甘辛い味わいがクセになります。
【材料(2〜3人分)】
・れんこん 150g
・ごま油 小さじ2
・醤油 大さじ1.5
・みりん 大さじ1
・砂糖 小さじ1
・白ごま 適量
【作り方】
-
れんこんは薄切りにして水にさらす(5分)。
-
フライパンにごま油を熱し、れんこんを炒める。
-
醤油、みりん、砂糖を加えて絡め、白ごまをふる。
冷蔵保存で約4〜5日持つので、常備菜として非常に便利です。おにぎりの具やお弁当のすき間埋めにも大活躍。
ごぼうと鶏肉の甘辛煮
ボリュームも栄養も満点な「ごぼうと鶏肉の甘辛煮」は、食べ応えがあり、メインとしても使える常備菜です。
【材料(2〜3人分)】
・ごぼう 1本
・鶏もも肉 150g
・醤油 大さじ2
・みりん 大さじ1
・酒 大さじ1
・砂糖 大さじ1
・水 100ml
・生姜(千切り) 適量
【作り方】
-
ごぼうは斜め切りにし、水にさらす。鶏肉は一口大に切る。
-
鍋に油を熱し、生姜と鶏肉を炒める。ごぼうも加えて炒める。
-
調味料と水を加え、落とし蓋をして中火で15分ほど煮る。
冷蔵で5日ほど保存可能で、冷凍すればさらに長持ちします。夕食のおかずにもう一品欲しい時にも重宝します。
これらのレシピはすべて冷蔵保存で数日持つうえに、ごはんが進む味付けなので、忙しい平日の食卓にもぴったり。次回は「醤油漬けレシピ」を紹介しますので、ぜひチェックしてみてくださいね!
箸が止まらない!醤油漬けレシピ
忙しい日々の中でも、ひと手間で食卓が一気に豊かになる「醤油漬け」。
素材の旨味を引き出しながら、保存も利くため、作り置きにもぴったりな万能常備菜です。今回は、その中でも特に人気のある3品、「にんにく」「卵黄」「きゅうり」の醤油漬けをご紹介します。

にんにく醤油漬け
スタミナ満点!香ばしくてクセになる味わいが魅力のにんにく醤油漬けは、調味料としても、副菜としても活躍します。
【材料】
・にんにく 1玉(10片程度)
・醤油 100ml
・みりん 大さじ2
・鷹の爪(輪切り) 少々(お好みで)
【作り方】
-
にんにくは皮をむき、軽く潰してから煮沸消毒した瓶に入れる。
-
醤油とみりんを鍋で一煮立ちさせ、粗熱を取る。
-
にんにくの入った瓶に注ぎ、冷蔵庫で3日以上漬け込むと食べ頃。
冷蔵保存で約1ヶ月もち、チャーハンや炒め物のアクセントにも使えます。
卵黄の醤油漬け
とろりと濃厚な「卵黄の醤油漬け」は、おつまみやごはんのお供として人気急上昇中。
【材料】
・卵黄(新鮮なもの) 2〜4個
・醤油 大さじ2
・みりん 大さじ1
【作り方】
-
卵を割って卵黄だけ取り出し、キッチンペーパーの上で軽く水分を取る。
-
清潔な容器に調味料を合わせ、卵黄を静かに入れる。
-
冷蔵庫で24〜48時間漬けたら完成。
ポイントは、卵黄が崩れないよう優しく扱うこと。濃厚な味が白ごはんにぴったりで、リピーター続出の一品です。
きゅうりの即席醤油漬け
パパッと作れてシャキッとおいしい、夏にぴったりの副菜です。
【材料】
・きゅうり 2本
・醤油 大さじ2
・酢 大さじ1
・砂糖 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・白ごま、鷹の爪(お好みで)
【作り方】
-
きゅうりは斜め薄切りにし、軽く塩をふって5分置いたら水気を絞る。
-
他の調味料と一緒に密閉袋やタッパーで和える。
-
冷蔵庫で30分ほど漬けたら食べ頃。
そのまま副菜にも、おつまみにも、アレンジにも便利な一品です。1〜2日で食べ切るのがベストですが、漬け時間が長いほど味がなじみます。
これらの醤油漬けは、どれも手軽なのに旨味たっぷり、しかも保存も効くという万能レシピばかり。冷蔵庫に一品あるだけで、料理の幅が広がります。
次回は「佃煮」編をお届けしますので、どうぞお楽しみに!
ごはんが進む!醤油ベースの佃煮レシピ
ごはんのお供といえば、やはり「佃煮」。特に醤油ベースの佃煮は、旨味と甘辛さが絶妙にマッチし、冷蔵庫に常備しておくだけで食卓が豊かになります。ここでは、定番の「昆布」「しいたけ」「小魚」を使った、簡単で美味しい佃煮レシピをご紹介します。

昆布の佃煮
だしを取った後の昆布を捨てるのはもったいない!佃煮にすれば、食物繊維たっぷりのヘルシー常備菜に早変わりします。
【材料】
・出汁を取った後の昆布 100g
・醤油 大さじ2
・みりん 大さじ1
・酒 大さじ1
・砂糖 大さじ1
・白ごま 適量
【作り方】
-
昆布は細切りにし、鍋に調味料をすべて入れて中火で煮る。
-
汁気が少なくなり、照りが出てきたら白ごまを加えて完成。
冷蔵で10日ほど保存可能で、おにぎりの具や、和風パスタのトッピングにもおすすめです。
しいたけの甘辛煮
乾燥しいたけを使えば、旨味がギュッと詰まった保存食になります。戻し汁も調味料として使うことで、無駄なく美味しさを活かせます。
【材料】
・乾燥しいたけ 5枚(戻して使用)
・戻し汁 100ml
・醤油 大さじ2
・砂糖 大さじ1.5
・みりん 大さじ1
【作り方】
-
しいたけを水で戻し、石づきを取って薄切りにする。
-
鍋にしいたけと戻し汁、調味料を入れて中火で煮詰める。
-
汁気が少なくなるまでじっくり煮て完成。
ごはんだけでなく、お弁当やうどん、そばのトッピングにもぴったり。冷蔵で1週間ほど日持ちします。
小魚の甘露煮風佃煮
ちりめんじゃこや煮干しを使った甘露煮風の佃煮は、カルシウムもたっぷり摂れる栄養満点な保存食。お子様のおやつにも人気です。
【材料】
・ちりめんじゃこ 50g
・醤油 大さじ2
・みりん 大さじ2
・砂糖 大さじ1
・白ごま 適量
・くるみやアーモンド(あれば) 適量
【作り方】
-
フライパンにちりめんじゃこを入れて乾煎りし、軽く水分を飛ばす。
-
調味料を加えて弱火で煮詰め、白ごまやナッツを加えて照りが出たら完成。
冷蔵で1週間保存でき、カルシウム補給にも◎。おにぎりに混ぜ込んだり、お茶漬けにするのもおすすめです。
どの佃煮も、ごはんが止まらなくなるおいしさで、毎日の食事に彩りと満足感を与えてくれます。次回は、発酵の力を活かした「醤油麹レシピ」をご紹介しますので、どうぞお楽しみに!
発酵の力!醤油麹の作り方と活用法
近年、発酵食品の健康効果が見直される中で注目されているのが「醤油麹」。
シンプルな材料で作れるのに、旨味とコクがグッとアップする万能調味料です。毎日の料理が格段に美味しくなるこの醤油麹、実は自宅でも簡単に作れてしまいます!

基本の醤油麹の作り方
手作り調味料として初心者にも人気の醤油麹。必要な材料はたったの2つです。
【材料】
・米麹(乾燥タイプ) 100g
・醤油 150ml(麹がしっかり浸る量)
【作り方】
-
清潔な保存容器(瓶など)に米麹を入れ、手でよくほぐす。
-
醤油を加えてよく混ぜ、麹全体に醤油が行き渡るようになじませる。
-
容器に蓋をして常温で保存。毎日一度かき混ぜ、1週間ほどで完成。
気温によって発酵速度が変わるため、夏は5日程度、冬は10日ほどかかることもあります。完成するととろみが出て、香ばしい発酵の香りが漂います。
醤油麹の保存方法と日持ち
発酵が完了したら冷蔵保存に切り替えましょう。しっかりと密閉すれば、冷蔵で約1ヶ月はおいしく使えます。
以下の表は、醤油麹の保存方法と保存期間の目安をまとめたものです:
| 保存方法 | 容器タイプ | 保存期間の目安 |
|---|---|---|
| 常温(発酵中) | ガラス瓶または陶器 | 約5〜10日(発酵期間) |
| 冷蔵 | 密閉容器 | 約1ヶ月 |
| 冷凍 | 小分け容器・製氷皿 | 約2〜3ヶ月 |
冷凍保存すれば小分けにして、必要な分だけ解凍して使えるのでとても便利です。解凍後も風味が保たれやすいのが特徴です。
野菜や肉料理への応用レシピ
醤油麹は、漬け込み・炒め物・ドレッシングなど多用途で活躍する調味料です。
以下に、おすすめの使い方をいくつかご紹介します。
1. 鶏むね肉の醤油麹漬け
鶏むね肉1枚に対して醤油麹大さじ2をまぶし、30分〜一晩漬けた後、焼くだけ。
驚くほど柔らかくジューシーに仕上がります。
2. 醤油麹ドレッシング
醤油麹大さじ1、酢小さじ1、ごま油小さじ1を混ぜるだけで、サラダや冷奴にも合う万能ドレッシングに。
3. 野菜の浅漬け風
きゅうりや大根を醤油麹で和えて30分置くだけ。麹の甘味が野菜の旨味を引き立て、箸が止まりません。
発酵食品ならではの風味と栄養が楽しめる醤油麹は、まさに「食卓の味方」。少量でも料理の味をぐっと引き締めてくれるので、常備しておくと重宝します。
次回は、「醤油保存食を美味しく長持ちさせるコツ」をご紹介します。保存方法に自信がない方も、ぜひチェックしてみてくださいね!
醤油保存食を美味しく長持ちさせるコツ
醤油を活用した保存食は、味わい深く、常備菜や作り置きとして大変重宝します。しかし、せっかく手作りした保存食も、保存方法を誤ると風味が落ちたり、劣化が早まることも。
この章では、保存食を安全に、そして美味しく長持ちさせるための基本をご紹介します。

瓶詰・冷蔵保存・冷凍保存の違い
保存食にはさまざまな保存方法がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあるため、料理や用途に応じて使い分けることが大切です。
| 保存方法 | 特徴 | 向いている食材 | 保存期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 瓶詰 | 真空密閉することで常温保存も可能。開封後は冷蔵必須。 | 佃煮、醤油麹 | 常温で数ヶ月、開封後は冷蔵で1〜2週間 |
| 冷蔵保存 | 手軽で日常的。多くの醤油系保存食に適している。 | 醤油漬け、きんぴら | 5日〜2週間程度 |
| 冷凍保存 | 長期保存に最適。風味が多少落ちることもある。 | ごぼう煮、肉の漬け込み | 約1ヶ月 |
冷蔵と冷凍をうまく使い分けることで、保存食のローテーションもラクになります。作った日付を容器に記載しておくと、食べ忘れ防止にもなります。
保存容器の選び方と衛生管理のポイント
保存食の味と鮮度を保つためには、容器の選び方と衛生管理が非常に重要です。以下の点を意識してみましょう。
1. 保存容器は「密閉できる」「清潔に保てる」ことが第一
-
おすすめ素材:ガラス瓶、ホーロー、プラスチック(耐熱性があるもの)
-
避けたい素材:においや色が移りやすい安価なプラスチック容器
特に醤油系の保存食は香りや色が強いため、容器に残りやすく劣化の原因になりがち。ガラスやホーロー素材なら、におい移りが少なく長く使えます。
2. 容器は使う前に必ず「煮沸消毒」または「アルコール消毒」
-
煮沸:熱湯で5分程度
-
アルコール:食品用エタノールで内側を拭き取る
どちらも乾燥させた状態で保存食を詰めることが重要です。
3. 「取り出すときのスプーン」にも注意
保存食を取り出すときには、乾いた清潔なスプーンを使うのが鉄則。濡れたままだと雑菌が繁殖する原因に。
保存だけでなく“取り扱い方”にも気を配ることで、最後まで美味しく安全に楽しめます。
保存のコツを押さえることで、醤油保存食はさらに便利で安心なものになります。手間をかけた分、きちんと管理して最後のひと口までおいしくいただきましょう。
まとめ|醤油の保存食で日々の料理が豊かに!
ここまで、醤油を使った保存食の魅力をたっぷりとご紹介してきました。常備菜として日々の食事を支える「醤油煮」や「きんぴら」から、ごはんが止まらない「佃煮」、さっと作れて便利な「醤油漬け」、さらには発酵食品として注目される「醤油麹」まで、多彩なレシピが登場しました。
これらの保存食は、ただ長持ちするだけではありません。醤油ならではの深い旨味が、どんな食材にも寄り添い、手軽なのに“しっかり美味しい”一品に仕上がるのが最大の魅力です。

保存食だからこそ広がる“おいしさと安心”
冷蔵庫にストックがあるだけで、忙しい日でも安心。お弁当作りに悩んだとき、もう一品欲しいとき、あと一口ごはんが欲しいとき…。醤油の保存食は、そんな“ちょっと困った”を助けてくれる心強い存在です。
さらに、今回紹介したレシピは、すべて家庭で簡単に作れるものばかり。特別な調味料や道具は必要なく、いつものキッチンで誰でも気軽にチャレンジできます。
保存の工夫で、もっとおいしく・もっと安心に
保存期間を把握し、容器や衛生面に気をつけることで、保存食はさらに美味しく、そして安全に楽しめます。冷蔵・冷凍の使い分けや瓶詰テクニックも押さえておけば、保存の失敗も防げます。
また、「いつ作ったか」をラベルで記録しておくこともおすすめです。自分や家族の食生活を管理する上でも、大きな助けになります。
醤油の保存食は“日本の知恵”の結晶
醤油という調味料は、日本の食文化の中で古くから親しまれ、保存性・味わい・栄養価の三拍子そろった万能調味料です。
その醤油を活かした保存食は、まさに昔ながらの知恵と、現代のライフスタイルが融合した「賢い食のかたち」。
忙しくても、体に優しいものを食べたい。そんな願いを叶えてくれるのが、醤油の保存食です。
これからの食生活に、ぜひ「醤油の保存食」を取り入れてみてください。小さな瓶詰やタッパーの中にある一品が、毎日の食卓をぐっと豊かに、そして心も満たしてくれるはずです。
最後までお読みいただきありがとうございました!
この記事を参考に、ぜひ今日から“ちょっとした保存食習慣”を始めてみてはいかがでしょうか?
出典情報
-
農林水産省|食材の保存と衛生管理
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/featured/hozon/ -
公益社団法人 日本食品衛生協会|食品の保存方法
https://www.n-shokuei.jp/





